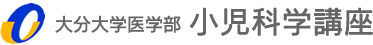腎疾患

グループ紹介
臨床
大分大学小児科腎臓グループでは、ネフローゼ症候群、IgA腎症などの慢性糸球体腎炎、ループス腎炎、尿細管疾患、急性腎障害、慢性腎臓病などの腎疾患や神経因性膀胱、膀胱尿管逆流症、水腎症などの泌尿器疾患の診療も行っています。
また、夜尿症診療も行なっています。腎生検数は、ガイドラインの改訂や腎疾患に対する新規治療薬の使用によって、当科では年間5件前後と数は以前より減っています。
教育
月1回新規患者さんについての情報共有と腎臓に関連する論文の抄読会を行っており、治療方針の確認と最新の腎診療のトピックスについて情報共有を行ないつつ、新たな研究テーマについて協議を行なっています。
また、神戸大学が主体で行っている腎生検カンファレンスに月1回参加をしています。
研究
小児腎臓病においては、希少疾患をゼブラフィッシュモデルを作成しながら、病態解明を行います。さらに、臨床研究としてIgA腎症の発見契機として学校検尿の意義を九州圏内の腎生検症例をまとめています。
求められていること、今後のミッション
腎疾患の多くは慢性疾患であり、長期間にわたり疾患と付き合わなければなりません。さらに腎疾患の治療として使われるステロイドは、非常に有効な薬剤ではありますが、その反面、副作用にも注意をしなければなりません。
小児腎疾患の患者さんたちをみるうえで、大事なことは、「できるだけ健常なお子さんたちと同様の生活や体験をしてもらうこと」と、小児腎疾患の研修を行った施設の上司に言われ、その言葉は、私に強く響いています。
小児腎疾患についてのクリニカルクエスチョンを解明できるような研究を行いつつ、慢性疾患を抱えるお子さん、その家族の方々に寄り添いながら、より良い医療を提供をしていくために日々精進をしてくことが使命だと考えます。