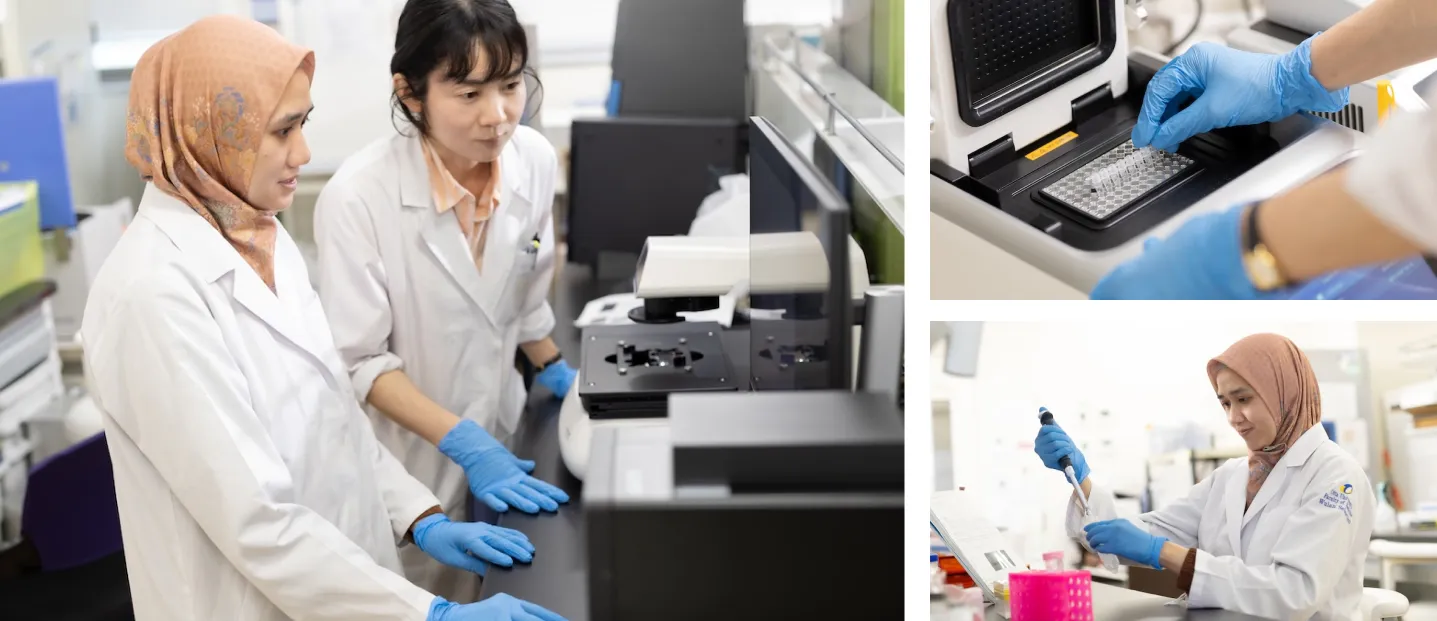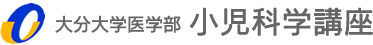研究紹介

研究概要
令和7年度日本学術振興会科研費(研究代表者のみ)
-
基盤研究C 井原健二
・ハッチンソン・ギルフォード早老症候群発症に関わる環境要因とオートファジー制御機構 -
若手研究 脇口宏之
・Blau症候群におけるアクネ菌病因論の構築 -
基盤研究C 前田知己
・自発運動(GMs)評価精度向上と実践体制構築を可能とする評価訓練システムの開発 -
基盤研究C 井上真紀
・乳児肝不全症候群1型における炎症増悪機序と治療標的の解明 -
基盤研究C 清田今日子
・Dent病の腎機能障害のメカニズムを解明する -
基盤研究C 小林修
・乳児の自発運動行動評価を用いた、神経発達症の遠隔早期発見健診システムの構築 -
基盤研究C 平野直樹
・ABSIによる内臓脂肪指標と循環器疾患発症予測に関する横断・縦断研究 -
基盤研究C 後藤洋徳
・小児AYA世代の白血病治療に対するヒストン脱メチル化阻害薬治療の実装化を目指す
-
若手研究 松田史佳
・発達障がいに合併した小児1型糖尿病児の自立支援プログラムの開発 -
基盤研究C 小栗沙織
・臨床的意義不明の変化と判定された小児と保護者への遺伝カウンセリング体制の構築 -
若手研究 Wulan Sebastian
・Characterization of dominant negative ACTA2 variants : a zebrafish model for nonsyndromic aortic aneurysms -
基盤研究C 塚谷延江
・がんゲノム医療における地域版遺伝看護教育プログラムの有効性の検証 -
基盤研究C 池内真代
・ゼブラフィッシュatp6v1ba遺伝子変異による耳石形成障害と難聴の機序解明 -
基盤研究C 島田祐美
・新生児スクリーニング偽陽性例に潜因する飢餓の発育への影響:母乳育児支援体制の構築
大分大学医学部小児科学講座の研究活動
ハッチンソン・ギルフォード症候群とは
ハッチンソン・ギルフォード症候群は、乳幼児期から急速な老化現象を呈する極めて稀な遺伝性疾患です。出生時には明らかな病状を認めませんが、生後間もなくから強皮症様の皮膚変化や関節の拘縮が徐々に出現し、著しい成長障害を認めるようになります。さらに、骨粗鬆症、若年性動脈硬化、心筋梗塞、脳卒中など、多岐に渡る加齢に関連した臨床症状を呈します。こうした病状が幼少期から顕在化することから、ハッチンソン・ギルフォード症候群はヒトの老化の分子機構を解明する上で貴重なモデル疾患としても注目されています。
日本における遺伝性早老症研究―AMED横手班を中心に
日本医療研究開発機構(AMED)の研究班(旧・横手班、現・前澤班)を中心として、遺伝性早老症に関する調査研究が継続的に進められています。ウエルナー症候群、ハッチンソン・ギルフォード症候群、ロスムンド・トムソン症候群について、臨床情報の集積、患者登録、診断基準の整備、治療法の開発に向けた基礎研究など、国際的にも高く評価される研究体制が構築されています。
疫学研究 ― 全国調査
大分大学小児科では、全国の医療機関の協力のもと、ハッチンソン・ギルフォード症候群患者を対象とした全国疫学調査を実施しました。日本国内の患者数、診断年齢、合併症の実態などを明らかにし、国内の診療体制の現状と課題を把握するとともに、今後の包括的な医療体制の整備を目指しています。
患者家族調査 ― 社会的・心理的支援の探究
ハッチンソン・ギルフォード症候群の患者さんとご家族を対象に、医療面に加え、日常生活や教育・福祉などの社会的支援に関するアンケート調査を実施しています。医療従事者に限らず、教育・福祉関係者とも連携し、日本の実情に即した包括的な支援体制の構築を目指しています。
基礎研究 ― ゼブラフィッシュモデルの作成
老化に関連する分子病態の解明と新規治療法の開発を目的として、ハッチンソン・ギルフォード症候群のゼブラフィッシュ疾患モデルを作製しています。このモデルを用いて、疾患の発症・進行機構の解析や、新規治療候補物質の評価を行い、臨床応用につながる基盤的知見の創出を進めています。
若手研究者の育成と国際連携
学内外の研究機関との共同研究を積極的に推進するとともに、国際学会や米国の家族会への参加・発表を通じて、若手研究者の育成とともに世界的な研究ネットワークの形成を推進しています。
今後の展望
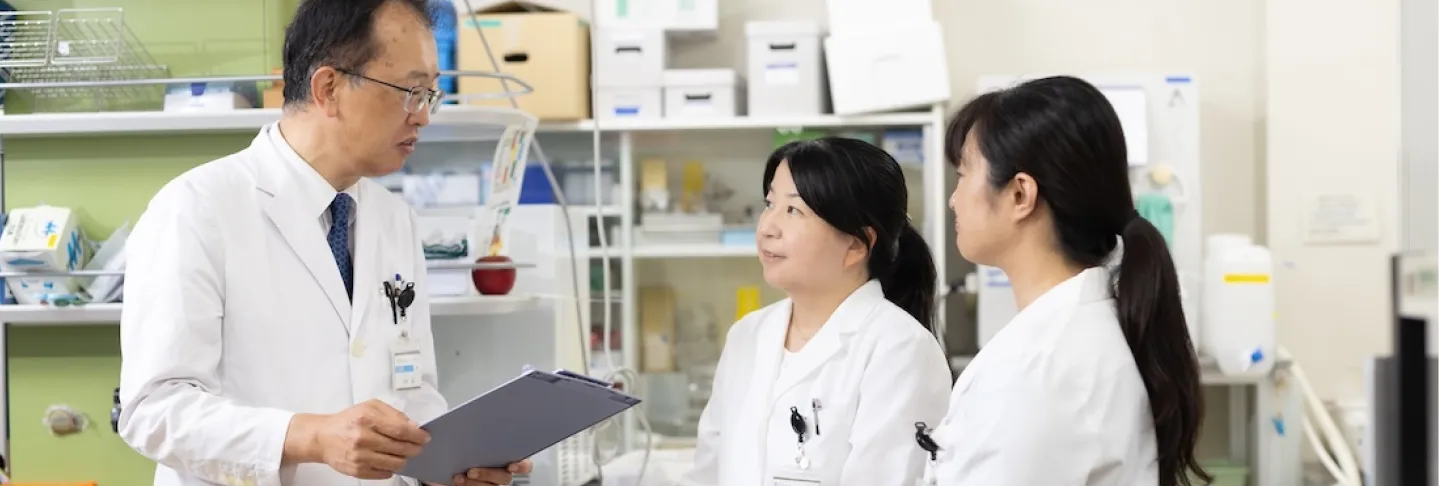
今後も国内外の研究者、医療関係者、患者団体と連携し、超希少疾患であるハッチンソン・ギルフォード症候群の診療および研究を推進します。患者さんとその家族が未来に希望を描けるような、臨床的・社会的に意義のある研究を目指します。